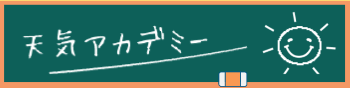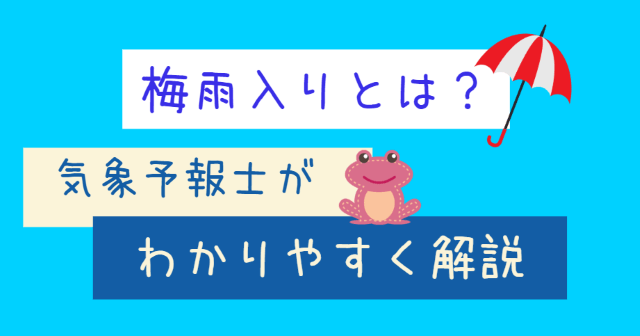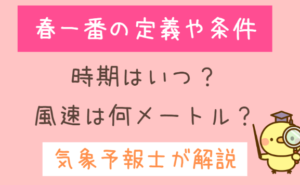こんにちは。気象予報士のともみです。
天気予報を見ていると、梅雨入りや梅雨明けって言葉を聞きますよね。
でも、いったいどういう時が梅雨入りで、逆に、どういった時が梅雨明けなのでしょうか?
ここでは、梅雨入りとは?について、わかりやすく解説します。
クリックできる目次
梅雨入りとは?

まず梅雨入りの前に、そもそも梅雨って何だ?
ということで、梅雨についてからお話します。
梅雨とは・・・
- 春から夏へと季節が移り行く中(6月から7月中旬頃)で、
- 雨やくもりの日が多くなり、
- 日照時間も少なくなる季節
のことをいいます。
日本だけのもののように思えますが、実は、日本以外でも、台湾や韓国、中国の華南・華中の沿岸部にも見られます。
この梅雨の時期。
天気は、2~3日の短い周期で変わり、大雨をもたらすこともあります。
特に、西や南の方で雨量が多くなり、梅雨末期には集中豪雨となることも多いので注意が必要です。
そして、この季節に入ったことを表すのが
梅雨入りなのです。

そして梅雨入りには、平均的に5日間ほどの「移り変わり」の期間があり、その中日を梅雨入り日としています。
ちなみに梅雨入りは、春一番のように風速何m以上とか、いつからいつまで等のの決まりがあるわけではありません。
参考
気象庁の方が天気予報を見て、この日が梅雨入りっぽいなと判断したら、
気象庁の職員さん
「〇月〇日が梅雨入り!」
と、梅雨入りの宣言をして決まります。
というのはわかったけど、どのようにして、 梅雨入りかを判断しているのかな?

気象庁の方は、梅雨入りの判断を次のようにしています。
- 前日や当日が「くもりか雨」
- 翌日以降も、週間予報などで「くもりや雨」のぐずついた天気が続くと予想される場合
たとえば
- 当日(6/15)が「曇りや雨」
- 前日(6/14)も「曇りや雨」だった
- 翌日(6/16)以降も「曇りや雨が続く天気」
こういった場合は、6月15日が梅雨入りとなります。
このため、梅雨入りの時期がはっきりしなくて、特定の日付がつけられない年もあります。
また、9月に、春から夏にかけての実際の天候経過を振り返って、梅雨入りの日が変更になることもあります。
では、その判断する気象庁の方って一体誰なのでしょうか?
梅雨入りを発表する気象庁の人は誰?

梅雨入りは、気象庁の方が、
数日~1週間の天候から判断して、日にちを決める、
とお伝えしました。
でも、気象庁って、47都道府県に気象台が置かれているんですね。
47都道府県それぞれの気象台の方が梅雨入りを出しているのでしょうか?
いえいえ、違います。
梅雨入りの宣言は、それぞれの47都道府県が行うわけではなく、各地方の予報中枢官署が行います。


以下が、梅雨入りの宣言を行う予報中枢官署です。
- 沖縄:沖縄気象台
- 奄美:鹿児島地方気象台
- 九州南部:鹿児島地方気象台
- 九州北部:福岡管区気象台
- 四国:高松地方気象台
- 中国:広島地方気象台
- 近畿:大阪管区気象台
- 北陸:新潟地方気象台
- 東海:名古屋地方気象台
- 関東甲信:東京管区気象台
- 東北南部:仙台管区気象台
- 東北北部:仙台管区気象台